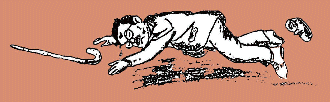
目の前で、家族や同僚が急に倒れた場合、あなたは何か「応急手当」ができますか?
生命に関わる「応急手当」のトレーニングを日頃から行っておけば、「いざ!」という時に、即座に対応できるでしょう。
誰にでもできる簡単な「応急手当」を知らないことによって、「尊い生命」を失う残念なケースは、まだ まだ多いのが現状です。
「こんな時!」、あなたはどう対応しますか?
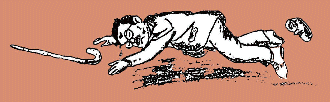 目の前で、家族や同僚が急に倒れた場合、あなたは何か「応急手当」ができますか? 生命に関わる「応急手当」のトレーニングを日頃から行っておけば、「いざ!」という時に、即座に対応できるでしょう。 誰にでもできる簡単な「応急手当」を知らないことによって、「尊い生命」を失う残念なケースは、まだ まだ多いのが現状です。 |
「万一!」呼吸や心臓が停止したら、
停止から「3分間」がとても重要です!
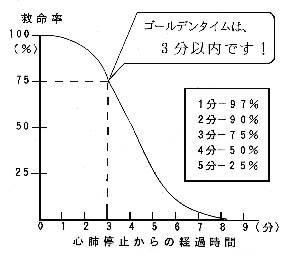 この表は、心臓発作・喘息など原因がどうであれ、人が急に倒れて「呼吸」や「心臓」が停止してから救命手当を開始するまでの時間経過と救命率の関係を表したものです。(外傷によるものは、該当しません。) 呼吸・心臓がともに停止すると、脳への血液の流れが止まってしまいます。 この場合、脳細胞は急激に死滅してしまい、死んだ脳細胞は絶対に元には戻りません。 「尊い生命」を救命するには、心肺停止から「3分間」が勝負です。 救急車の到着を待っていては、「救命」は不可能です。 |
家族や同僚が倒れた場合、
可能性にかけてABCを行いましょう!
目の前で人が倒れた人、倒れている人を発見した場合、一刻も早く、今から行う「心肺蘇生法」を適切に実施しなければ、家族の「尊い生命」は救命できません。
今から行う「救命手当」は、簡単で誰にでもできます。
まず、落ち着いて下さい!(パニック状態になるのは当然ですが!)
倒れた人の状態をしっかり観察して、それに応じた適切な手当を救急車が到着するまで行うことによって、救命率は随分と高くなります。
<救命手当の手順>(1人法)
倒れた人、倒れている人を発見したら!(救命手当の手順)
落ち着いて、「意識」を確認!
 まず、傷病者の肩をたたきながら、耳元で呼びかけます。(声は、徐々に大きく、3〜4回呼びかける) 傷病者が「眼を開けたり」「手で払いのけたり」「しかめる顔」などせず、全く反応がなかったら、「意識なし」と判断して下さい。 |
大声で「助け」を呼ぶ!
 「意識なし」と判断した場合は、周りの人に「誰か来て!救急車をお願いします!」と大声で助けを呼んで下さい。 次に、傷病者の「口」を手でしっかり開きます。 |
しっかり口を開いて、口の中を確認!
  口の中、のどの奥の方に「食べ物」や「吐いた物」がないか確認して下さい。 |
吐いた物などは、しっかりかき出す!
 もし、吐いた物などがあったら、顔をゆっくり横に向けて、手指でのどの奥まで、しっかりかき出して下さい。 かき出したあとは、もう1回のどの奥の方をしっかり見て、吐いた物などが残っていないか確認しして下さい。 口の中やのどの奥に何もないことを確認したならば、次のA・B・Cの手順で「救命手当」を行います。 このA・B・Cの救命手当を行う場合も、確実な「観察」が必要です。 |
意識がない!
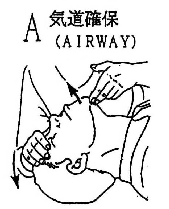 口の中やのどの奥に「何もない」ことが確認されたら、左図のように額に手置いて、もう一方の手指2本(人差し指と中指)で、傷病者の下アゴ先にひっかけるようにあて、額の手を押さえながら下アゴ先を引き上げます。 この要領で、空気の通り道を確実に開放してやります。これを「気道確保」といいます。 この要領で「気道確保」を保ちながら、耳を傷病者の口・鼻のところに近づけて、呼吸音を聞きながら、頬(ほっぺ)で空気の出入りを確認し、眼で胸の上下運動をみます。 呼吸の有無を確認するのは、「5秒間」です。(落ち着いて、声を出して!) この方法で、呼吸をしていない場合は、「呼吸なし」と判断して、次の人工呼吸を開始します。 |
呼吸がない!
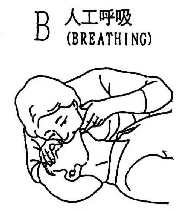 「呼吸なし!」と判断した場合は、まず人工呼吸をゆっくり2回行います。 人工呼吸とは、呼吸が停止している人に対して、人工的に外から呼吸させてやる方法をいいます。 こ方法は、気道確保を継続しながら、額側の手指で傷病者の鼻をつまんで、自分の口を大きく開けて、傷病者の口に覆うようにあてがって、ゆっくり自分の「吐く息」を送り込んでやります。 約1リットル程度を約2秒間かけて、胸の動きを見ながら吹き込みます。(この時、胸が少しあがれば十分です。) 特に1回目は、空気の入り具合を十分に確認しながら行ってください。 この要領で、連続して2回吹き込みます。 もし、吹き込む際に、「ゼロゼロ」というような変な音がしたら、のどの奥に何か異物があるので、再度、のどの奥を確認して下さい。 呼吸の吹き込みを2回行ったら、傷病者の脈拍を確認して、心臓が動いているかどうかを確認します。 確認する部位は、「総頸動脈」です。 |
「脈拍」の確認は、あわてず確実に!
 しっかりした部位に手指2本を縦にあて、総頸動脈の拍動を約5秒間確認します。 この部位の確認方法は、額の手はそのまま、、アゴ先の手を離して指2本を気管にあて、そこから手前に滑らせて移動し、気管の横のくぼんだ部分に指先を少し押すようにあてます。 もし、わかりにくい場合は、片手で気管をつかむようにして、気管の横のくぼんだ場所に手指(2本)を残して押しあてます。 1才未満の乳児の確認は、上腕動脈や大腿動脈を手指で押さえて行います。 これで、拍動が触れなかったら「心臓停止」と判断して、心臓マッサージを開始して下さい。 しっかりした拍動が確認されたら! これらの部位で、脈拍が触れている場合は、心臓が動いていますので、人工呼吸のみを5秒に1回行います。 1〜10才の幼児・小児の場合は、4秒に1回。1才未満の乳児では、3秒に1回の割合で人工呼吸を行います。 |
脈拍がない!
圧迫部位は正確に!
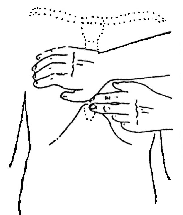 心臓マッサージを開始 心臓の部位を正確に確認します。 まず、足側の手指2本をみぞおちの上端に置き、その横にもう一方の手(付け根部分)を並べるように置きます。 その上から足側の手を組むようにして重ねます。(手の平から先は、少しあげる。) この圧迫する部位がずれていると、心臓マッサージの効果が薄れますので、確実に行って下さい。 万一、気が動転してわからなくなった場合は、「胸の真ん中」「お乳とお乳の真ん中」でも、十分に効果があります。 |
深さ・スピードは正確に!
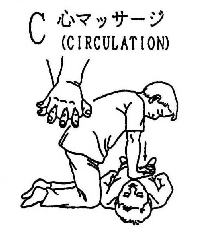 「心臓停止」と判断したら、即座に心臓マッサージを開始します。 この心臓マッサージは、停止した心臓を身体の外から力を加えて、人工的に心臓を動かそうとする方法です。 <注意> 注1 肘はまっすぐに伸ばす 2 腕は床面と垂直に 3 膝は開いて身体を安定させる(つま先は立てる) 4 顔色や身体などの動きがないか確認しながら行う 押す強さは、成人や10才以上の小児の場合、胸が約4〜5cm沈む程度で、毎分80〜100回のペースで行います。 10才程度までの幼小児の場合は、片手で約3cm、リズムは同様です。 1才未満の乳児の場合は、手指2本で垂直に約2cm沈むように、毎分100〜120回のリズムで圧迫します。 これらの方法で、人工呼吸と心臓マッサージをリズムや回数を守って交互に行い、救急隊に引き渡すまで頑張って継続します。 |
心肺蘇生法
心肺蘇生法とは、人工呼吸と心臓マッサージを併用した方法をいいます。
ここでは、周りに心肺蘇生法を知っている人がいないことを想定して、成人に対する「1人法」を説明します。
<1人で行う場合>(1人法)
最初に2回の人工呼吸の後は、心臓マッサージ15回・人工呼吸2回を繰り返します。
10才未満の幼小児や乳児の場合は、2回の人工呼吸の後は、ともに心臓マッサージ5回・人工呼吸1回を繰り返します。
<まとめ>
これらのリズム・回数・強さなどについては、<まとめ>をクリックして下さい。
<注意事項>
1 心肺蘇生法を開始してから約1分経過(4セット実施)したら、必ず脈拍や呼吸の回復状況を確認して下さい。(それ以降は、
2〜3分ごとに確認!)
2 脈拍がしっかり触れて、顔色も良くなってきたら心臓マッサージを中断して下さい。
3 呼吸の方は、しっかりした楽な呼吸をしていれば、中断して下さい。
4 脈拍・呼吸ともにしっかり回復しても、意識が戻らなければ、気道確保を継続するか身体と顔をともに横に向けて寝かせて、食物などを吐いたりしないか見ていて下さい。
5 心肺蘇生法実施中や中断後に胃の内容物を吐かないか厳重に注意して下さい。
<救命講習を受講しておいてね!>
万一に備えて、最寄りの消防署が行う「救命講習会」を受講し、救命手当を修得しておきましょう。
一家に一人の「応急手当修得者」をめざし、会社・各種団体・町内会などを通じて、救命講習会に参加して、「尊い生命」を家族ぐるみで守りましょう。
上記の文章をダウンロードされる方は、下の画像をクリックして下さい。